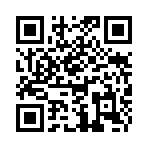2007年01月07日
七草粥
今日は七草ですね、皆さん食べましたか七草粥

君がため春の野に出て若菜(七草)摘む わが衣手にゆきはふりつつ
【 光孝天皇 】
百人一首でなじみ深いこの歌に出てくる若菜とは春の七草のことです。
一月七日は七草の日。
「人日(じんじつ)の節句」「七草の節句」ともいわれ今では「七草粥」を食べる日になっていますが、もともとの原形は中国から伝わったもので、旧暦の一月七日は、新年の占い始めの日であるとともに朝廷や幕府に年賀を述べる日でした。平安時代に「七草粥」を食べることが慣例になり、江戸時代では、五節句(1/7人日の節句、3/3上巳の節句、5/5端午の節句、7/7七夕の節句、9/9重用の節句)の一つとして、将軍、諸侯が七草粥を食べる公式行事になりました。時代とともに占いから「七草粥」に重点が移り、この日に「七草粥」を食べると邪気が払われ、無病息災でいられるという慣習になっていきました。
「七草なずな 唐土の鳥が 日本の土地に 渡らぬ先に…トントンバタリ トンバタリ…」その昔、人々は六日の夜に七草を刻みながら七草ばやしを歌う風習がありました。唐土の鳥というのは、大陸から疫病をもたらす渡り鳥のことで、渡り鳥が日本に着く前に海に落してやろうと歌ったものです。害鳥を追い払いその年の豊作を願う考えが、七草粥の行事と混ざり合ったものと思われます。

君がため春の野に出て若菜(七草)摘む わが衣手にゆきはふりつつ
【 光孝天皇 】
百人一首でなじみ深いこの歌に出てくる若菜とは春の七草のことです。
一月七日は七草の日。
「人日(じんじつ)の節句」「七草の節句」ともいわれ今では「七草粥」を食べる日になっていますが、もともとの原形は中国から伝わったもので、旧暦の一月七日は、新年の占い始めの日であるとともに朝廷や幕府に年賀を述べる日でした。平安時代に「七草粥」を食べることが慣例になり、江戸時代では、五節句(1/7人日の節句、3/3上巳の節句、5/5端午の節句、7/7七夕の節句、9/9重用の節句)の一つとして、将軍、諸侯が七草粥を食べる公式行事になりました。時代とともに占いから「七草粥」に重点が移り、この日に「七草粥」を食べると邪気が払われ、無病息災でいられるという慣習になっていきました。
「七草なずな 唐土の鳥が 日本の土地に 渡らぬ先に…トントンバタリ トンバタリ…」その昔、人々は六日の夜に七草を刻みながら七草ばやしを歌う風習がありました。唐土の鳥というのは、大陸から疫病をもたらす渡り鳥のことで、渡り鳥が日本に着く前に海に落してやろうと歌ったものです。害鳥を追い払いその年の豊作を願う考えが、七草粥の行事と混ざり合ったものと思われます。
Posted by toshi at
12:47
│Comments(0)